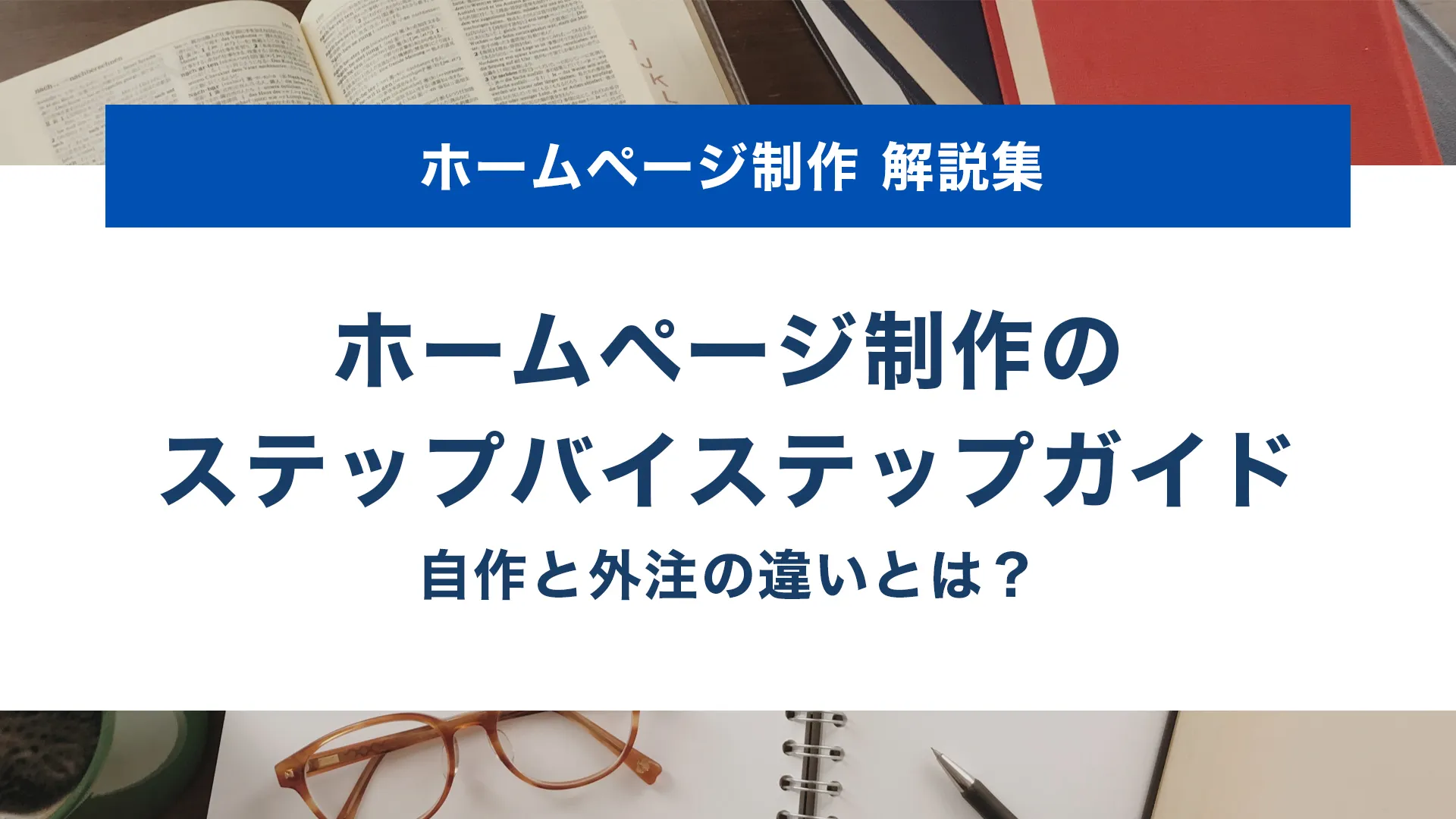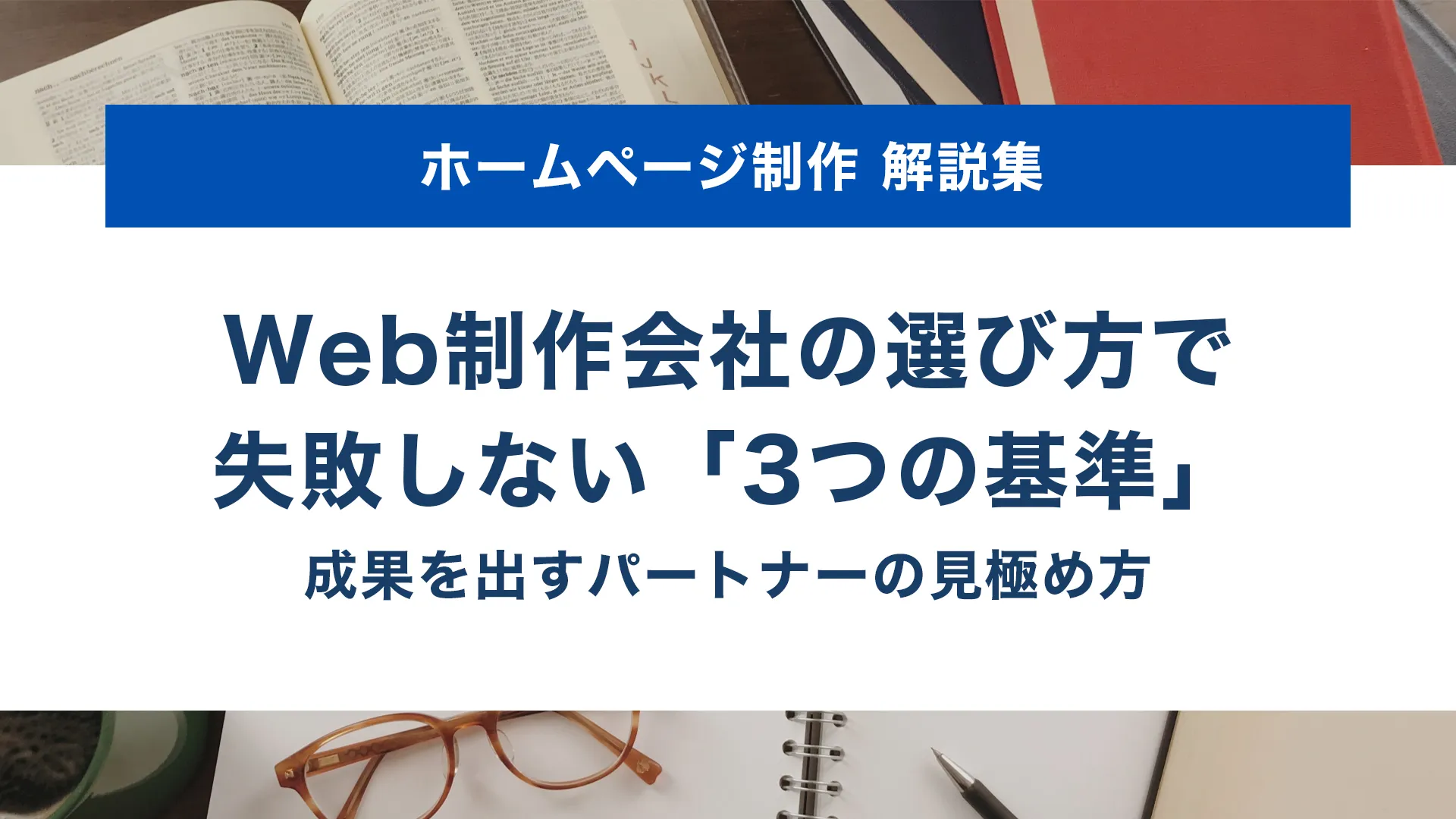ホームページ制作を依頼する前に知っておきたい流れ・費用相場・制作会社の選び方
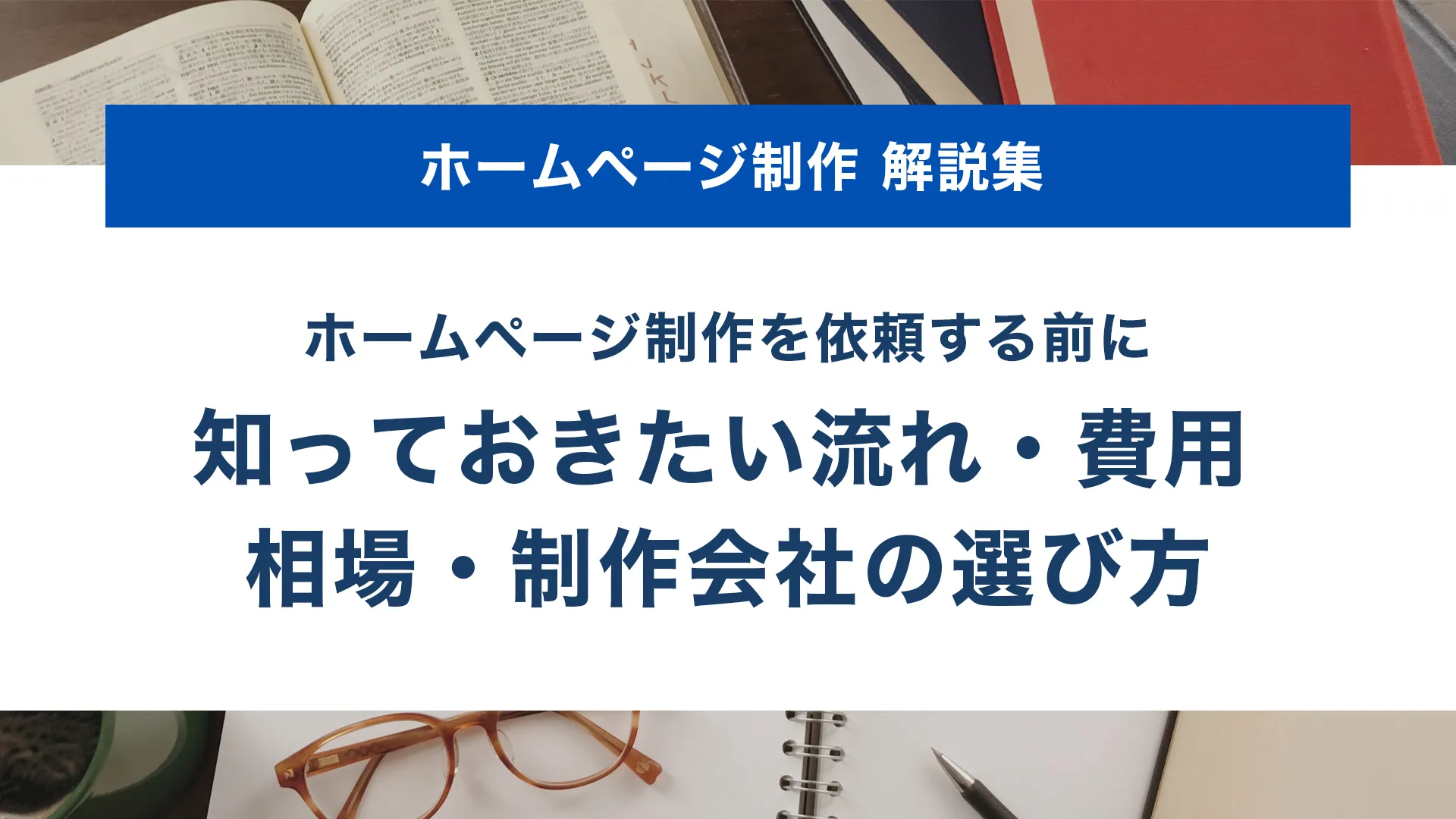
万が一あなたがWeb業界の方だという話でなければ、いざ「ホームページを制作したい」となっても、何から始めたらいいのかわからない、となるのは不思議なことではありません。
「ホームページ制作」というミッションを完遂させるには最低限、「制作の流れ」・「費用の相場」・「制作会社の選び方」などを把握していないと、いつまでにどのような準備が必要かもわからず、満足のいくホームページを手に入れることは難しくなってしまうでしょう。
本稿では、より良いホームページを手に入れるために、ホームページ制作を外部の業者に依頼する際に知っておくべき必須事項を解説します。「制作の流れ」・「費用の相場」・「制作会社の選び方」を理解し、理想のホームページを手に入れてください。
【事前準備】ホームページ制作依頼前の流れ

ホームページ制作を依頼する際には、事前準備が必要です。
ページ数や機能数によって異なりますが、事前準備には約2~3週間かかります。事前準備の期間をふまえて、ホームページを公開したい日から逆算して動き始めましょう。
何を目的とするホームページなのかを明確にする
新たに人材を採用したい、ホームページから集客したいなど、ホームページを制作する目的を明確にしましょう。
何を目的としたホームページなのかを明確にすることで、ホームページに入れるべき機能やデザインがはっきりします。
ホームページ制作の目的としてあげられる代表例は、以下の通りです。
・ブランディング
・見込み客の増加
・自社商品・サービスの紹介
・求人募集
ホームページ制作会社によって、デザインやマーケティングなど得意とする分野が異なります。目的が明確であれば、自社のホームページ制作に適した業者を判断しやすくなります。
ホームページ制作の担当者やチームを決める
制作会社に依頼した後もデザインの変更や要望の追加など、制作会社と自社との間では細かなやりとりが発生します。
社内のホームページ制作担当者やチームを決めておき、スムーズにやりとりができるようにしておきましょう。
ホームページ制作担当者やチームを決めておけば、進捗確認や意見のすり合わせがしやすくなります。また、窓口が1つになることで、認識のズレも起こりにくくなり、「思っていた仕上がりと違う」となってしまうことを避けられます。
ホームページの目的や解決したい課題をまとめた資料を作る
ホームページを作る前に、目的・解決したい課題・予算・納期などを整理し、これらの情報をまとめた書類「RFP(提案依頼書)」を作成しましょう。
RFPを作成しておくことで、自社の要望や方針を正確に伝えやすくなります。また、文章として残るため、伝達トラブルや認識のズレを防止可能です。
制作会社とホームページの方向性を共有し、スムーズに制作を進めるためにも、準備資料として活用しましょう。
予算と依頼範囲を決めておく
ホームページは、ページ数や搭載する機能が増えたり、凝ったデザインにしたりすると、費用が増加します。予算の上限を決めておけば、予算の範囲内で必要なページや機能を検討できるため、気づいたら膨大な費用がかかっていたといった事態を防止できます。
また、予算の上限を制作会社に伝えておくことで、予算内で自社に適した提案をしてもらうことも可能です。
加えて、制作会社に依頼する範囲も明確にしておきましょう。自社でできる作業は自社で対応し、できない部分だけを依頼することで費用を抑えられます。
依頼範囲が決まれば予算も自ずと明確になるため、予算と依頼範囲はセットで考えることが重要です。
依頼する制作会社を決め、見積もりをとる
依頼を検討する制作会社を3〜5社程度に絞り、見積もりをとりましょう。あまり多くの制作会社に見積もりを依頼すると比較の手間が膨大になるため、無闇に選択肢を増やしすぎるのはおススメできません。
できるだけ正確な見積もりをとるためには、制作会社に依頼する作業範囲が確定した後に行いましょう。
依頼する作業範囲が決まっていないうちに見積もりをとると、おおよその見積もりとなり、正確な金額がわからないからです。
また、見積もり依頼と一緒に、「提案書」の提出も依頼することをおすすめします。提案書とは、ホームページ制作の目的や発注者の課題をどのように解決するかを示した書類です。
見積書だけでは費用しかわかりませんが、提案書と併せて確認することで、見積書の項目の詳しい内容や作業範囲などを把握できます。提案内容が自社の目的とあっているかどうかを確認するためにも大切な書類です。
金額だけを比較するのではなく、自社の目的にマッチした提案かどうか、自社の課題解決ができるかどうかにも注目して依頼する制作会社を選びましょう。概ね金額が安過ぎる制作会社は表面上それっぽいホームページを作成できても、マーケティングツールとして意味のあるホームページを制作することはできません。
【発注〜納品】ホームページ制作依頼後の流れ

依頼の事前準備が終わると、いよいよ実際にホームページの制作作業に入ります。
発注から納品までは、ペライチの簡単なものでも(まっとうにマーケティングツールとして意味のあるものに仕上げるのであれば)約2週間〜1か月ほどかかります。ページ数や作業量が多い場合は、2〜3か月程度かかることも少なくありません。
制作会社に発注する
依頼する制作会社が決まったら、ヒアリングが実施されます。発注者の目的や課題、完成イメージなどを詳細に聞き取り、共有します。
ヒアリングのときに詳細を伝えられるように、ホームページの完成イメージや導入したい機能、デザインの方向性を決めておきましょう。
「こんなホームページを作りたい」という参考ページがあれば、制作会社に見せながら説明するのも一つの方法です。
全体のサイト設計をする
ヒアリングの内容をもとに、制作会社がサイトマップとワイヤーフレームを作り始めます。
サイトマップとは、ホームページの全体像を客観的に把握できるよう図で表したものです。どのようなコンテンツがどの階層にあるのか、どのカテゴリーにあるのかをわかりやすく伝えます。
一方、ワイヤーフレームは、何を・どのような所に・どうやって配置するかを表した各ページの設計図です。
たとえば、トップページの上部に「企業理念」の文字を配置し、その下の右側に社員の集合写真、左側に会社紹介文を入れるといったように、ページ全体のレイアウトを図で表します。
サイトマップとワイヤーフレームを活用することで、依頼側と制作会社で共通認識を持ちやすくなり、思ったような仕上がりにならなかったという事態を防止します。
また、情報が整理されるため、必要なページが抜けていないか、わかりにくい導線になっていないかの確認も可能です。
ホームページに載せる原稿や写真などを準備する
全体のサイト設計ができたら、原稿や写真などのホームページに載せる素材を用意し、制作会社に提出します。原稿や写真の他に、準備が必要な素材には、以下のようなものがあります。
・イラスト
・動画
・グラフに使う数値データ
・参考資料
自社で素材を準備する余裕がない場合は、制作会社に依頼したり、ライターなどへの外注も可能です。
ホームページのデザインを作る
発注者が素材を用意している間に、ヒアリング内容や参考サイト、ワイヤーフレームをもとに、制作会社がデザインを制作します。
この段階では、実際の素材がまだ揃いきっていない事が多いため、写真や文章は仮のものを使って制作するのが一般的です。
デザインの作成は、都度発注側に確認をしてもらい、必要に応じて修正を加え、再度確認をしてもらうといった流れで進みます。一気に完成の形まで仕上げることはあまりありません。
途中でデザインの大きな変更がある場合は、追加費用がかかる可能性があります。デザイン確認の段階で丁寧にチェックし、チーム内で共有しておきましょう。
その際、チームだけでなく、最終的に承認できる上司や決定権を持つ人にも確認を依頼し、共有することも大事です。
チーム内だけで進めてしまい、後から「イメージと違う」と差し戻しになると、スケジュール遅延や追加費用の原因につながります。
実際に稼働するホームページのシステムを開発を制作する
ホームページをデザイン通り実際に稼働させるため には、以下の作業が必要になります。
・コーディング作業
・表示・動作チェック
サーバとは、ホームページなどのデータを保管し、インターネットを通じて利用者が閲覧できるようにするためのコンピューターです。たとえば、検索欄にURLを入力すると、そのページのデータが保存されているサーバから情報が送られ、画面に表示されます。
ドメインは、URLのうち、「https://」や「http://」の後ろに続く部分です。「https://sample-site.jp/index.html」であれば、「sample-site.jp」の部分がドメインです。ネットの世界ではドメインを使って目的のサイトを探し当てます。
コーディング作業では、デザインデータをもとに、実際にブラウザ上で動くホームページを構築します。HTML、CSS、JavaScript、PHPなどのプログラミング言語を使い、見た目のレイアウト・動作・アニメーション・フォームなどの機能を実装していきます。
コーディングには専門的な技術が必要なため、基本的に制作会社が担当するケースがほとんどです。発注側は、細かな修正指示や進行確認をします。
コーディング作業が終わると、デザインが想定通りに表示されているか、ボタンが正常に動くかなどをチェックします。表示・動作チェックをすることで、リンク切れや表示崩れなどの不具合を事前に発見でき、スムーズな公開が可能です。
納品
全ての作業が終わり発注側の確認が取れたら、ホームページを公開し、納品完了です。
ただし、ホームページは公開して終わりではありません。ドメインとサーバ-の維持やアクセス分析、コンテンツ制作など、継続的な保守と運用が必須です。
保守・運用も含めて、制作会社に依頼するかどうかを決めておきましょう。公開後の不具合への対応や、更新作業の手間や費用が大きく変わるため、事前に運用方針を明確にしておくことが大切です。
ホームページ制作を依頼する場合の費用相場
ホームページ制作を依頼する場合の費用相場は、以下の通りです。
・約10ページ:約60万円~
・約20ページ:約90万円~
ページ数のほかにも、ホームページの目的や機能によって費用は変動します。たとえば、会社概要や事業内容を紹介するだけのシンプルなサイトであれば、比較的安価です。
SEOや集客を意識したサイトは、コンテンツ設計や分析ツールの導入が必要なため費用が上がります。商品検索や会員ページ、決済機能などを導入する場合は、システム開発が発生するため、高額になっていきます。
ここで挙げた相場はあくまでも株式会社GoFでの制作相場であり、より高い会社も安い会社も存在はします。上でも触れましたが、概ね金額が安過ぎる制作会社は表面上それっぽいホームページを作成できても、マーケティングツールとして意味のあるホームページを制作することはできないことが多いので、慎重に検討をしてください。
ホームページ制作会社の選び方
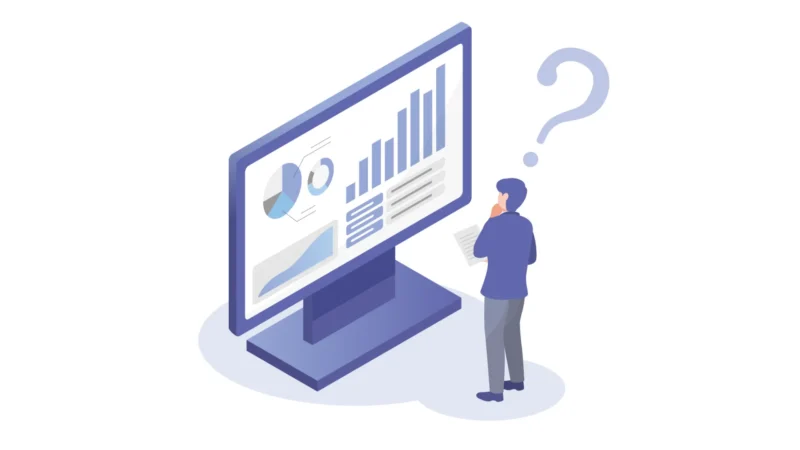
初めてホームページ制作を依頼するとなると、どのような会社に依頼すれば、理想通りのホームページが制作できるのかわからず、悩んでしまうのも無理はありません。
筆者なりの失敗しづらい「ホームページ制作会社の選び方」を提案します。決して安い買い物ではない「ホームページ制作」。悲しい結果になってしまわないように、慎重に信頼できる制作会社を選んでください。
依頼したい制作会社のサイトの完成度は高いか
まず確認したいのは、制作会社自身のホームページの完成度です。自社サイトが整っていない会社に依頼しても、理想のホームページを作ってもらえるか不安が残ります。
サイトのデザインやレイアウトが見やすく整っているか、掲載されている情報がわかりやすいかをチェックしてみましょう。
ブログやお知らせの更新頻度が高く、ターゲットに届く内容を発信しているかも重要なポイントです。定期的に有益な情報を発信している会社は、マーケティングにも力を入れていると判断できます。
サイトの内容から、どのような業種の制作を得意としているか、採用や実績紹介などにどれだけ力を入れているかも確認しておくと安心です。自社の強みをしっかり表現できている会社は、クライアントの魅力を引き出す力にも期待できます。
自社の希望を取り入れつつロジカルに提案してくれるかどうか
「ホームページ制作」というサービスにおいては、表面上のカタチも大事ですが、それよりも「マーケティングツールとしての機能」がより重要な要素であり、これは≒「制作担当者の論理的思考法」自体でもあります。
「この機能を追加するとユーザーの利便性が上がります」「このページ構成を減らすと見やすくなります」など、専門家として確固たるロジックの通った助言をしてくれる会社でなくては「なんとなく表面上は動いている」ホームページしか出来上がってきません。
少しでも気になる点があれば、なぜそうなるのか聞いてみて、納得の得られる回答をし続けられる相手であるかどうかを見定めることが何より重要です。
担当者の相性とコミュニケーションが問題ないか
ホームページ制作は、依頼から公開まで数か月かかることがあります。長くやり取りを重ねるからこそ、担当者との相性やコミュニケーションの取りやすさを確認しておきましょう。
次のような点をチェックしておくと安心です。
・専門用語を使わず、初心者にもわかりやすく説明してくれるか
・自社の事業に興味を持ち、積極的に意見をくれるか
・ヒアリングの時間をしっかり設けてくれるか
担当者が、自社スタッフか外部パートナーかも確認しておきましょう。外部の人が対応する場合、情報共有のズレや責任の所在が曖昧になることがあります。自社スタッフが、どこまで関与しているのかを把握しておくと安心です。
制作会社の強みと自社の目的がマッチしているか
制作会社は、それぞれ得意分野が異なります。自社が叶えたい目的を明確にし、それを実現できる強みを持った制作会社を選びましょう。
たとえば、採用に強いサイトを作りたいのに、ブランドイメージを重視したデザイン系の制作会社に依頼しても、期待した結果が出ないことがあります。
制作会社の得意分野を見極めるには、次のような方法があります。
・記載がない場合は、直接「どのようなジャンルの制作が得意か」を聞いてみる
自社の目的に合った制作会社を選ぶことで、成果の出るホームページづくりにつながります。
実績が豊富にあるか
制作会社を選ぶ際は、単に実績数の多さだけでなく、実績の中身を確認することが大切です。
自社と同じ業界や、採用強化や問い合わせ増加、EC売上アップなど、似た目的の実績があるかをチェックしましょう。制作実績ページで成果が数値で示されていたり、課題と解決策が具体的に紹介されていたりする会社は、提案力が高い傾向があります。
打ち合わせの際に以下のような質問をしてみると、その会社の実力が見えやすくなります。
・そのサイトで成果が出た理由は何か
・似た課題を持つ企業に、どのような提案ができそうか
実績を通して課題をどう解決してきたか説明できる会社を選ぶと、より安心して任せられます。
納品後のサポートやフォローがあるか
ホームページは公開して終わりではなく、運用や改善を続けることで成果につながります。そのため、納品後のサポート体制やアフターフォローがあるかも制作会社選びの重要なポイントです。
たとえば、次のようなサポートが用意されている会社は安心です。
・Googleアナリティクスなどをもとに、改善ポイントを定期的に報告してくれる
・更新や不具合など、困ったときに迅速に対応できる窓口が整っている
制作会社のサイトを見て、運用代行やサポートがあるか確認し、具体的なサポート内容や期間、料金をチェックしましょう。
予算と納期の希望が通る会社かどうか
ホームページ制作会社によって、料金体系や納期の基準が異なります。自社で、いつまでに・どのくらいの費用で制作したいのかを明確にし、見積もり時に伝えましょう。
予算内でどこまで対応してもらえるのか、公開までにどのような工程が必要なのか、修正や追加費用の条件なども確認することが大切です。これらを把握しておくことで、納期の遅れや想定外の費用発生を防げます。
流れを理解して理想のホームページを制作しよう

ホームページ制作を成功させるには、事前準備から納品までの流れを把握しておくことが欠かせません。目的や課題の整理・予算と依頼範囲の明確化・RFPの作成など、準備段階を整えておくことで、理想に近いホームページを実現できます。
理想のホームページを想像しながら、信頼できる制作会社を見つけて、自社にぴったりのホームページを形にしていきましょう。
「自分たちで調べてみたけれど、どこの制作会社に依頼したらいいのかわからない…」とお困りの際には、ぜひ私たち「株式会社GoF」へご相談ください。
「株式会社GoF」は、コスパの高いWebマーケティングとデザインの力でホームページ制作を行う会社です。初めての方でも安心してご依頼いただけるようフェアなサービスと丁寧なコミュニケーションで、お客様のリソースを最大限に活かす、戦略と分析に基づいた効果の高いwebサイトを安価かつスピーディーに提供します。
最初は無料のヒアリング・診断を行っておりますので
まずは現状確認もかねて一度お気軽にお声がけください。
投稿者
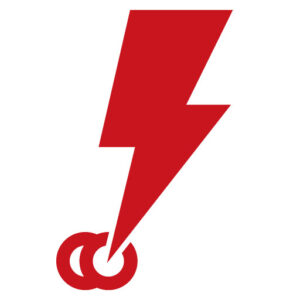
藤岡 聡
元々オタク向けのフィギュアを製造したり、原型をOEMで他社に提供する会社(株式会社Questioners)を経営していたが、色々なエンタメ商材を取り扱っているうちに自分の仕事の本質がマーケティングにあることに気づき「株式会社GoF」を設立。現在はWeb制作からマーケティング全般をサービスとして提供。